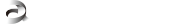【I Don't Like Mondays.】自分たちらしさを追求したアルバム『RUNWAY』
9月6日、5thアルバム『RUNWAY』をリリースするI Don't Like Mondays.。昨年、『ONE PIECE』の主題歌「PAINT」で幅広い層にアピールし、海外での評価も高まった彼らがこのタイミングで放つアルバムは、どんなコンセプトで制作されたものなのか? メンバー4人にジックリとお聞きしてみました!
『RUNWAY』というタイトルに込められた意味と思いとは……

──今回のアルバムタイトルは『RUNWAY』ということですが、この言葉自体は早くにツアーのタイトルで公表されていたものでした。その時点でアルバムタイトルとして決定していたのでしょうか?
YU はじめから、アルバムとツアーはそのタイトルでいこうという話になっていて、順番がそうなったというだけですね。
──では、そもそもこの『RUNWAY』というタイトルの意図はどういうところなんでしょう?

YU 去年、2022年に、僕らがトライする楽曲たちというのをひと通りやり終わったなと思っていて。その中で、『ONE PIECE』の主題歌の「PAINT」という曲の存在も大きかったんですよね。そこから入ってくる新しいファンの方がいたり、日本の活動がメインだったので、日本の音楽シーンの中で僕らが提示できる音楽を追求していこうということで、2022年まではやってました。
それが、「Black Thuderbird TOUR」という形でいったん区切りがついた段階で、じゃあ次の2023年はどういうものを軸にして自分たちの活動をやっていこうかということを、年末ぐらいからずっと考えてたんです。その中で、僕らが次にやるべきことっていうのは、改めて「自分たちらしいもの」をもう一度追求していくということじゃないかと。「じゃあ、“自分たちらしさ”って何なんだろう?」という話し合いの中で、ファッションだったり、ファッションショーに招待されてそこに行くまでのワクワク感だったり、そういうものを音楽のライブでも感じてもらいたいなという、サウンドだけじゃなくて雰囲気だったり匂いだったり、そういうものも自分たちで表現したいなという思いがあったので、そういうワード、自分たちらしいものを探そうよという中で「RUNWAY」という言葉が出てきたんです。
改めて、僕らが突き進んでいきたい、自分たちらしく歩いていきたい道でもあるし、音楽というものをそれぞれのシーンで身にまとって見える景色……いつもと同じ景色が、その音楽があることによって、違って見えたり、魅力的に見えたりとか。そんな風になったらいいなという思いで、このタイトルが一番ベストなんじゃないかということになりました。
──そうやって伺うと、『RUNWAY』という言葉は「それしかないな!」と思うんですけど、実際にはスムーズに出てきたワードだったんですか?
YU そのワードそのものというよりも、「自分たちがどういう活動をしていこうか」という話し合いをさんざんしていて。その中で、たまたま僕がそのワードを出させてもらったんですけど、悩んで出したというよりは、「あ、こういうワードいいな」と。字面もいいし、自分たちが考えているいろんな意味を持たせられるなということで、「これどう?」ってメンバーに言ったら「あ、それいいじゃん」って形で、そこはわりとすんなり決まりました。
──今回、既発曲が5曲あって、アルバムで初公開の曲が4曲ありますよね。その中で「アルバム」としての方向性というのはどの段階からあったものなんでしょう?
YU 今までは、けっこうギリギリの段階で「こういうアルバムにしていこう」みたいなのを決めてたんですけど、今回は去年「ダイナマイト」という曲を出した時点でうっすらあったんですよ。2月に配信したシングル1曲目の「WOLF VIBES」の時から「『RUNWAY』というタイトルがいいんじゃないか」という話はしていたので、今年出した曲は全部、そこに向けて作ってます。僕らとしてはそんなに早いのは初めてなんですけど(笑)。
KENJI アルバムを想定して配信してたという感じですね。
──それだけ早くから想定できたというのは、活動に余裕ができたからですか?

SHUKI というよりは、ブランディングというか、僕らの軸を固めるのが一番大事な年だなと思って。去年は「PAINT」っていうアニメ『ONE PIECE』の主題歌があって、曲調とか今までで一番いろいろと振り幅を出したので、そこで年が変わってひと区切りしたタイミングで、逆に今の僕らがどういうものかを見つめ直した方がいいんじゃないかということで軸を作ったので、逆に迷いはなかったですね。
配信してたシングルってタイアップも多かったので、外的な要望を中心に自分たちの音楽を作って形にしてきたんですけど、「ダイナマイト」を作ったきっかけが、「ツアーの1曲目になる曲がない」ってことだったんですよ。その時はアルバムが出てからのツアーというわけではなかったので、じゃあどういうツアーにするかということで、自分たちがやりたかった80'sのムードで作ったんですよね。そこから次の「WOLF VIBES」の時にアー写を撮り直して、よりファッションに寄ったというか。その写真と自分たちのテンションに合った音楽ということで作り始めて、みんなもそうだと思うんですけど、僕もその等身大な感じがしっくり来て、それが『RUNWAY』というところにつながったんですけど、だからけっこう自然な流れで今に至っているかなという感じですね。
──アー写から曲へ、ということもあるんですね。
YU 客観的に自分たちを眺めるきっかけというか、手法の一つというか。アー写もジャケットも写真も、僕らの中では一つの表現方法ですからね。バンドって、そういうパッケージで楽しめるものだと思うので、そういう意味での楽しみ方もしたいねと。
SHUKI 今までの僕らがやってきたことがけっこう幅広かったので、今年は逆にちょっと絞って僕ららしさを出していこうということで、「WOLF VIBES」の時から、「アー写の僕らに合った曲ってどういう曲だろう?」ということをイメージしながらやってきました。
──では、アー写の撮り方一つにもけっこう時間をかけているわけですね。
YU それも、「アー写をどう撮るか」というよりも「どこに行けば自分たちっぽいか」ということなんですよ。好奇心もあったりして、いろいろ試したくなる自分たちもいるんですけど、そこで自分たちの気持ちが先に行っちゃってクリエイターがついてこれなかったら意味がないんで、1回抑えるというか、向かう先を、自分たちらしさを追求するクリエイティブに集約しようと。詞も、音楽も、写真も全部そこに向かうようにしようと。そういう風にできたら、来年はより自分たちらしさを出せるよねというのを、年末ぐらいに考えてました。

CHOJI 今までは単発のクリエイティブ・ファーストだったんですけど、今回は僕らファーストで、それをクリエイティブに落とし込むという逆のやり方に集約していきましたね。
──では、今回はトータルで思い描いた形にできたわけですか。
YU そういう意味では、そうですね。もしかしたらそれ以上のものかも。今までは考えすぎてたんですよ。「これを出したらどういう風に見られるか」とか。そういうのの限界も感じてて。だから今回は具体的に「こうなるだろう」という予想はせず、いい意味でそういう外的な条件は無視して(笑)。たぶん、自分たちが心地いいと思うものが、自分たちのやりたいことなので、その心のセンサーみたいなものに注意深く目を向けて歌詞を書いたり、メロディーのアイデアを出したりしていきました。
世界での経験を通してバンドを成長させてくれた「PAINT」
──先ほどからちょくちょく出ている「PAINT」ですが、『ONE PIECE』の主題歌になったこともあって、アイドラがより広く知られるきっかけになったと思います。その影響をどう感じていますか?
YU 一番は、日本で今まで僕らのことを知らなかった人たちに届いたという驚きよりも、海外に行けたということの方が、自分たち的には大きいですね。あの曲によって、海外に行く機会が実際にできて、海外でのライブで「PAINT」以外の曲もメチャクチャ盛り上がったりしてくれてるのを見て、「ああ、これでよかったんだ」という自信につながったということの方が、あの曲から得たものとしては大きいかなと思いますね。

KENJI 海外でも活動していきたいという思いは当初からあったんですけど、この「PAINT」という曲を『ONE PIECE』を通して作ったことによって、いろんなところに行く機会にも恵まれましたし、日本でもフェスには出てますけど、それより大きな場所だったりで自分たちを試す機会が生まれて、その中でしっかりとしたパフォーマンスを発揮することが僕たちの糧になったと思うんですよね。これから日本で活動する上でも必要なプロセスだったし、勉強させてもらえたなというところで「PAINT」には感謝してます。
──海外のフェスで評価されたりすると、自分たちのやってきたことが間違いじゃなかったという気持ちにもなりますよね。
YU それはすごくなりました。どうしても自分たち4人のルーツは洋楽がメインで、「日本の音楽シーンに受け入れられるためにはどうしたらいいんだろう?」というところを試行錯誤してきた部分があるんですね。それがいい意味で吹っ切れたというか、今後もクリエイティブの実験として楽しみながらやる分にはいいんですけど、そこで変に頭を悩ませながら曲を作るのは、本来あるべき姿じゃないなと思っていて。僕が音楽でやりたいのは、その曲を聴いてテンションが上がったりとか、もっと本能的なところなんですね。「このビートでこの旋律だったらみんなが聴きやすいんじゃないか」みたいなことよりも、もっと本能的なところにたどり着けるような曲を作っていきたいんです。そういう意味では、こんな機会をもらって曲を作って、海外にも出してもらえたことで、変に考え過ぎる必要はないんだと、僕らがエネルギーを注ぐ場所はそこじゃないんだということが分かって。その結果、もっと僕たちらしいところに魂を注ぎ込むということに集中できるなと思いました。
──そういう意味でも「PAINT」は大きかったんですね。あの曲は「ザ・J-POP!」という曲調で新鮮でしたが、「アニソン」という側面は意識されたんですか?
YU しました。それで言うとあの曲って、「I Don't Like Mondays.さんに作ってもらいたい」と、僕らを名指しでいただいたオファーではないんですよ。まだそこのレベルに達してないという自覚は僕らにもあるし、そういう驕りはないんですが。ただそのチャンスはいただいたので、そこで僕らがそのチャンスを掴み取るためには、『ONE PIECE』という僕らが子供の頃から好きなコンテンツの良さを心から理解して、そこに寄り添えて、そのオープニングがより魅力的になる音楽じゃないと、僕らがやる意味がないと、すごく思ったんです。だからかなり研究して、でも僕らが奏でるものなので、どうしても僕ららしさみたいなものも出てしまうじゃないですか。そこは思いきりやろうとみんなで決めてやって、採用してもらったので。もしかしたら「アイドラっぽくないよね」って思う人ももちろんいるかもしれないし、そこから僕らを知ってくれた人もいるし。だから結果よかったなと思いますね。
──「らしくない」というよりも、正直「J-POPもガッチリやりこなすな」と思ったんですが(笑)。
一同 (笑)
YU ただ海外に行って思ったのは、世界の人たちって、「J-POP」だとか「洋楽」だとか、それすら考えてなくて、もっと本能的。
KENJI ジャンルがどうだとか言ってないよね。
YU 気付いてすらいないと思う(笑)。
──アルバムの話に戻りますが、前半は深めのアレンジの曲が多くて、終盤に「WOLF VIBES」「ダイナマイト」とアップテンポの曲が続きますよね。この構成というのは?
SHUKI やっぱり流れによって曲の聞こえ方も全然変わってくるので、一つひとつがよりよく聞こえるようにというのと、このアルバム自体、「僕らっぽさ」をより分かりやすく伝えたいというのがあったので、前半で特に今の僕らっぽいと思える曲を集めたというのもありますね。
YU 一番はやっぱり、「よく聞こえるには」というところですね。並びをミスると、同じ曲でも全然よく聞こえないので。そこを一番意識した結果、こうなりました。
──アルバムって、始まりと同様かそれ以上に終わり方も大事だと思うんですが、このアルバムではアガって終わるイメージですよね。
YU それで言うと「Beautiful Chaos」という曲は、もともと「ライブの最後の曲に似合うような曲を」ということで作ってたんです。しばらくの間、デモのタイトルも「ライブ最後の曲」ってなってたぐらいなんですよ(笑)。最後がバーッと広がっていくような曲なので、アルバムでも最後の曲になるのかなと思ってたんですけど、いろいろ並べ替えていった結果、「Summer Ghost」の流れからそこに入るのが一番よく聞こえるとなったので、そうしました。

CHOJI 「ライブの最後の曲」ということですけど、やっぱりシンセじゃなくてギターの方がバンド感を出せる楽器だと思うので、たくさんギターを入れました。その意味で、ライブでもやり甲斐のある曲になるんじゃないかなと思ってます。やっぱり「TONIGHT」はライブでもお客さんがすごく盛り上がるんですけど、それを超えるというか、また違う形でそういうのを提示できた曲になって、よかったなと思ってます。
──先ほども「ライブの1曲目になる曲がほしい」という話がありましたが、ライブの中での必要性みたいなところから作られる曲も多いんですか?
KENJI 今回、特に意識しましたね。前作の『Black Humor』を出した時はコロナ禍の中だったじゃないですか。みんなの聴き方も変わってきちゃって、ワイワイしたところで聴くというよりは、一人でじっくりという感じになりましたよね。だから僕らもけっこう試行錯誤して、「家でひとり聴きできるもの」というものに挑戦したんですね。そこから「Black Thunderbird TOUR」をやって、翌年はフェスとか海外でやらせてもらう機会があって、徐々に声を出せるようになった中で、「やっぱりライブって本来こうだったよな」というのがすごくあったんですよね。その中で、ライブをさらに楽しくできるような曲がほしい」というのはみんな思ってたと思うので、今回は特にライブでやるのが楽しみな曲が多いという印象ですね。
今回のアルバムで各メンバーが新たに挑戦したこととは?

──3曲目から6曲目は新曲が並んでいますが、「Beautiful Chaos」の次の「Strawberry Night」はESME MORIさんとの共作で、すごくダンサブルな仕上がりですね。
SHUKI これは、本当の原型はもうちょっと洋楽っぽかったよね。
KENJI そうだね。
SHUKI メロとかテンポ感は全然変わらないんですけど、今回のアルバムに向けてデモを何曲か作って、どれを入れようかという話をしていた中で、せっかくだから今年のトレンドっぽい、そのときしか作れない音楽も作りたいし、だったらどうせなら誰かと一緒にやりたいという話になって。僕とESME君は同い年なんですけど、今のトレンドに強い人とやりたいということでお願いしたら、快く受けてくださったんです。そこから僕らはデモを投げて、ただ「こうしてください」じゃなくて、極力ESME君の色を出したかったので、ホントに好きなようにやってくださいという感じで、そこから何回かやりとりして作り上げていった感じですね。
──共作ということでいうと、次の「conversation」もDPR CREAMさんの名前が入ってますね。
YU DPRという、韓国発で世界で活躍してるアーティストがいるんですけど、もともと僕らもすごくファンで、ライブとかも行かせてもらったりして動向をチェックしてるぐらいで(笑)、すごいクリエイティビティーなんですよね。アジアでこんなに世界に通用する人たちがいるんだなあということで、いつか一緒にやりたいと思ってる中で、たまたま、ひょんなことから「一緒にやれるよ」というお話をいただいて、是非ご一緒したいとお返事して、まずは編曲という形でとなりました。DPRの曲は全部聴いているので、DPR CREAMのよさが生きるような曲をデモの中から選んで作っていって、それに対して彼が「こういうのはどう?」という感じで返してくれて。今までだったら初めに決めたメロディーのまま最後まで行くんですけど、リアレンジされたものを聴いて「もっとこうした方がいいかも」ということで、けっこうメロディーも変えたりして、また彼もインスピレーションでいろいろ変えたりして。結局、この曲も自分たちだけだったら絶対生まれないよなというものになりましたね。DPRらしさもすごく出ていて、自分たちとしても「面白い曲ができたな」と思いました。
──今後も続いていきそうですね。
KENJI できれば嬉しいです。
YU できたら、ゼロから作るのもやってみたいなと思いますね。
──もう1曲の新曲が「Sin City」。こちらはビート感の強い曲ですね。
SHUKI そうですね。これはYUのファルセットが生きる曲がほしいなってとこからスタートして、声以外の要素が極力入らないように意識して作っていったんですけど、サビがパーッと開ける感じなので、その対比としてAメロ、Bメロはあんまり明るすぎないように……ダークまではいかないですけど、サビとのギャップを作ろうという感じにしました。ジャンル的に言うと「ディスコ」で、ディスコって昔からのイメージだとブラスが入ってたりして、照明も暖色系だったり、ブルーノ・マーズもライブではそういう感じでやってるんですけど、僕個人的には、僕らの今年のイメージが深い青だったりするんですね。だから明るすぎない印象の照明が映えるような曲を、イメージカラーというか、軸にして作っていったらけっこうトラックが作りやすくて。普通のディスコでいったらけっこう明るくなりがちなところを、「オレンジなのかもしれないけど、なるべく青に近づける」というか、そういうところを意識しました。
──この新曲を含むアルバムの中で、特に新しくやってみたことというのは?
YU 僕はDPR CREAMと一緒にやった「conversation」で、ラップのリリックをここまで本格的に書いたというのは初めてでした。今までは“ラップもどき”というか、あくまでバンドマンが書くリリックという感じだったと思うんですけど、せっかくDPRとやるんだったら、というのもあって。そこで気付いたのは、「普通の詞とは、使う脳が違う」ということでしたね。
──違いますか。
YU それぞれの難しさとか面白さがあるんですけど、本当に感情のままに言葉にできるのが、ラップ調のリリックのやり方なんだなというのを思いましたね。すごく楽しくやれて、だからこそ難しさもあったんですけど。あとは、普通だったらメロディーの音程が重視されるんですけど、ラップでは言葉だけの音程が、聴く人によりアプローチしてくるので、そのへんも、難しさであり楽しさでもあるのかなあと思いました。

KENJI 出来上がってみて思ったのは、今回はバンドらしさを大事にしようと言っていた中で、僕のベースは打ち込みの方が多くて(笑)。ドラムを生でやるか打ち込みでやるかの違いで、曲のバンドらしさってけっこう左右されると思うんですけど、今回は打ち込みっぽい曲でもSHUKIが生で叩いてる曲が意外に多いんですね。その中で、ちゃんとスピード感を出せるようにということで僕は打ち込みでやった曲が多いんですけど、そもそもベーシストなので、打ち込みよりは弾く方が得意なんですよ。だからすごく試行錯誤しました。『Black Humor』の時は邦楽というものをけっこう勉強したんですけど、今回は海外の打ち込みの曲をけっこう聴いたりして、「ベースの中でもこういう音色やフレーズがあるんだ」とか「こういう風に音をレイヤーすると、こう聞こえるのか」というのをインプットしたのを踏まえてアウトプットできたなと。そういうのが改めて勉強になりましたね。
──なるほど。
KENJI アルバムを通してだと「Sin City」が一番トライしてるというか。生のベースもスラップで入れてたりするんですけど、シンセベースの音が4つから6つ、セクションによってレイヤーされていて、それは本当にすごく実験的でしたし、僕の中でも「シンセベースってこういうものなんだ」というのを改めて考える、いい機会になったなという感じですね。

SHUKI 『Black Humor』の時は歌詞が伝わりやすいようにということで曲調から工夫して、そのために日本の音楽、その時にトレンドになってる音楽をいっぱい聴いたんですね。その中でやっぱり、AメロBメロサビというのが分かりやすい構成なんですけど、ボカロや宅録が流行ったりして、そういうルールにとらわれない方がいっぱい出てきて、そのへんの面白さをそこで学んで。洋楽って、自由な面もあるんですけど、形式的にはずっと一緒だったりして、変化が多すぎるものは少ないんですよね。転調とかも少ないし。という意味では今回のアルバム、特に新曲はあんまり頭で考えずに、その時いいと思うものをどんどん作ろうということで、洋楽だけ、邦楽だけという考え方ではできないような、けっこう自由な感じで作れたのはチャレンジというか、逆にそれがストレスなくて。聴いてる人も飽きずに聴けるものになったかなと思います。
──それはしかし、けっこうなチャレンジですよね。
SHUKI そうですね。考えるのを放棄したというか(笑)、カッコよければ何でもいいじゃん、っていう感じで作りました。
CHOJI 僕はどの曲にも、影響を受けたギタリストのフレーズとかを実は入れてたりしてて。「Summer Ghost」のエンディングはヴァン・ヘイレンだったり、「Sin City」もクール・アンド・ザ・ギャングのミュートリフを意識して弾いたりしてるんで、気付いてくれる人は気付いてくれるかなと。そういう風な楽しみ方もできるんじゃないかなと思います。「これはこれかな?」と思った人はツイッターなりで聞いてくれれば、正解を教えますんで(笑)。
「RUNWAY TOUR」ではより大きくなったバンド力を爆発させたい!
──アルバム自体の内容も充実してますが、同時に発売される「豪華盤」がDisc 2の楽曲もたくさんあるし、PHOTO BOOKも付属してて、文字通り豪華ですよね。
YU アルバムは2年ぶりになるんですけど、僕らはけっこう休まずに曲を作り続けてきたので、それが体感できたらいいなと。PHOTO BOOKとかも僕らのやりたい世界観が具現化できているので、そこも楽しんでもらえればと思います。
KENJI クリエイティブの統一という意味では、今までで一番できたんじゃないかと思いますね。
SHUKI この時代、音を聴くだけだったらCDである必要はないので、わざわざCDを出すということは、“もの”としても僕らの思いを伝えたいという意味で、僕らもけっこう気合いが入っちゃいましたね(笑)。
YU PHOTO BOOKに関しては、新しく一緒にやってるチームがあるんですけど、彼らとけっこう密に僕らの表現したい世界とかのことを話し合って、それをどう写真に落とし込むかというのは今まで以上に深くやりました。
──今までだって、ほかのアーティストやバンドと比べたらかなりこだわってる感じがありますが、それ以上なんですね。
YU そうですね(笑)。もっともっと突き詰められるところはあるなと思うんですけど、ようやく、僕らのやりたい世界観が実際のものとして世に出せる土台みたいなものができてきたなと思います。
──で、10月から12月にかけてはまたツアーですね。今お聞きしてきた中で、若干ヒントみたいなものもありましたが。
YU 僕らもまだリハーサルに入ってないので(※取材時点)、まだどんなものになるのかは分からないですけど、言えるのは、本当に去年とは比べものにならないぐらいパワーアップしているということですね。曲単体もそうだと思うんですけど、演奏もそうですし、バンド力みたいなものも海外での経験を通じて大きくなってるなと思うので、そういうものが爆発させられたらいいなと思ってます。
──繰り返しですが、海外での経験は本当に大きいですね。
YU 本当にそうですね。自分の中でも、枷みたいなものが取れた感じがします。
──ツアーと言えば、2月から3月にかけてはSELECTION TOURが行われましたよね。そこで気付いたことというと?

YU リクエストに本当に忠実にやろうと決めていたので、「バラードばっかりになったらどうしよう」とかいろんな懸念があったんですけど、やっぱり僕らのファンの方々は分かっていて、ちょうどいいバランスで曲をチョイスしてくれたので、ストレスなく楽しめました。さすが我々のファンだなと(笑)。
SHUKI 1位になったのが初期のアルバムに入ってる「LOVE YOURSELF」という曲だったんですけど……
YU あ、アレは意外だった! 癒やしを求めてるんだなと思いましたね。
KENJI あ、そういうことね(笑)。再生回数が多い曲が上に来るのかなと思ってたら、けっこう意外な結果になりましたね。
──今年の後半はツアーが中心という感じですか?
YU そうですね。ただ海外もあるし、まだ発表してないものもありますし。制作は一段落したので、基本的にはライブがメインにシフトしてくるかなと思います。まあ、曲もちょこちょこ作るとは思いますけど。
──その中で、今後こうしていきたいというのは?
YU やっぱりクオリティーを上げたいですよね。僕はボーカルのレベルをあと3段階ぐらい上げたいなと。
──3段階ですか。
YU 海外で活動していくとなると、バンドに甘えていられないというか(笑)。今までだったらノリで何とかできてたところも、よりクオリティーを求められるので。それは日本でもそうですけど。そこをレベルアップしていきたいなと思ってます。
KENJI 毎回、ツアーのたびに気づきがあって、成長もしていくと思うんですけど、今回久しぶりにライブを想定して作れたアルバムなので、いろんな経験も経て、とにかくこのツアーでバンド力をどれだけ引き上げられるかというのを徹底していきたいですね。海外も行くし、もっともっとバンドとしても成長していきたいと思ってます。
SHUKI 声が出せるツアーが久しぶりなので、本当に一体感が出せるような僕らのライブを作りたいし、それをもって来年の活動もなるべく迷いがなく進めるように、やりきりたいですね。
──毎年、「来年はこうしよう」という意識があるものなんですか?
SHUKI わりとありますね。
YU 今はアルバムができたばっかりですけど、もう僕の頭の中では「次はこうしよう」というのは何となくあります。
──それは素晴らしい。
YU ありがとうございます(笑)。僕は納期に遅れないタイプなので。
KENJI 早め早めは大事ですね。
──最後になりましたが、CHOJIさんはどうでしょう?
CHOJI せっかく『RUNWAY』というアルバムとそのツアーなので、ファッションを意識したライブを全国の皆さんにお届けしたいなと思っております。演出とかステージングとかも、もっと意味があるものになってくるかと思うので、楽しみにしていただければと思います。
──いろいろ楽しみなことが多いですね。ありがとうございました!

5th Album『RUNWAY』
2023.09.06 ON SALE
https://idlms.com/news/349401


I Don't Like Mondays. 2023 A/W TOUR "RUNWAY"
https://idlms.com/news/347726
【I Don't Like Mondays. WEB SITE】
https://idlms.com
【I Don't Like Mondays. YouTube】
https://www.youtube.com/idontlikemondaysofficial
【I Don't Like Mondays. Instagram】
https://www.instagram.com/idlms.official
【I Don't Like Mondays. Twitter】
https://twitter.com/IDLMs_OFFICIAL
【I Don't Like Mondays. TiKTok】
https://www.tiktok.com/@idlms_official?lang=ja-JP
【I Don't Like Mondays. Facebook】
https://www.facebook.com/rockidlms
『RUNWAY』というタイトルに込められた意味と思いとは……

──今回のアルバムタイトルは『RUNWAY』ということですが、この言葉自体は早くにツアーのタイトルで公表されていたものでした。その時点でアルバムタイトルとして決定していたのでしょうか?
YU はじめから、アルバムとツアーはそのタイトルでいこうという話になっていて、順番がそうなったというだけですね。
──では、そもそもこの『RUNWAY』というタイトルの意図はどういうところなんでしょう?

YU 去年、2022年に、僕らがトライする楽曲たちというのをひと通りやり終わったなと思っていて。その中で、『ONE PIECE』の主題歌の「PAINT」という曲の存在も大きかったんですよね。そこから入ってくる新しいファンの方がいたり、日本の活動がメインだったので、日本の音楽シーンの中で僕らが提示できる音楽を追求していこうということで、2022年まではやってました。
それが、「Black Thuderbird TOUR」という形でいったん区切りがついた段階で、じゃあ次の2023年はどういうものを軸にして自分たちの活動をやっていこうかということを、年末ぐらいからずっと考えてたんです。その中で、僕らが次にやるべきことっていうのは、改めて「自分たちらしいもの」をもう一度追求していくということじゃないかと。「じゃあ、“自分たちらしさ”って何なんだろう?」という話し合いの中で、ファッションだったり、ファッションショーに招待されてそこに行くまでのワクワク感だったり、そういうものを音楽のライブでも感じてもらいたいなという、サウンドだけじゃなくて雰囲気だったり匂いだったり、そういうものも自分たちで表現したいなという思いがあったので、そういうワード、自分たちらしいものを探そうよという中で「RUNWAY」という言葉が出てきたんです。
改めて、僕らが突き進んでいきたい、自分たちらしく歩いていきたい道でもあるし、音楽というものをそれぞれのシーンで身にまとって見える景色……いつもと同じ景色が、その音楽があることによって、違って見えたり、魅力的に見えたりとか。そんな風になったらいいなという思いで、このタイトルが一番ベストなんじゃないかということになりました。
──そうやって伺うと、『RUNWAY』という言葉は「それしかないな!」と思うんですけど、実際にはスムーズに出てきたワードだったんですか?
YU そのワードそのものというよりも、「自分たちがどういう活動をしていこうか」という話し合いをさんざんしていて。その中で、たまたま僕がそのワードを出させてもらったんですけど、悩んで出したというよりは、「あ、こういうワードいいな」と。字面もいいし、自分たちが考えているいろんな意味を持たせられるなということで、「これどう?」ってメンバーに言ったら「あ、それいいじゃん」って形で、そこはわりとすんなり決まりました。
──今回、既発曲が5曲あって、アルバムで初公開の曲が4曲ありますよね。その中で「アルバム」としての方向性というのはどの段階からあったものなんでしょう?
YU 今までは、けっこうギリギリの段階で「こういうアルバムにしていこう」みたいなのを決めてたんですけど、今回は去年「ダイナマイト」という曲を出した時点でうっすらあったんですよ。2月に配信したシングル1曲目の「WOLF VIBES」の時から「『RUNWAY』というタイトルがいいんじゃないか」という話はしていたので、今年出した曲は全部、そこに向けて作ってます。僕らとしてはそんなに早いのは初めてなんですけど(笑)。
KENJI アルバムを想定して配信してたという感じですね。
──それだけ早くから想定できたというのは、活動に余裕ができたからですか?

SHUKI というよりは、ブランディングというか、僕らの軸を固めるのが一番大事な年だなと思って。去年は「PAINT」っていうアニメ『ONE PIECE』の主題歌があって、曲調とか今までで一番いろいろと振り幅を出したので、そこで年が変わってひと区切りしたタイミングで、逆に今の僕らがどういうものかを見つめ直した方がいいんじゃないかということで軸を作ったので、逆に迷いはなかったですね。
配信してたシングルってタイアップも多かったので、外的な要望を中心に自分たちの音楽を作って形にしてきたんですけど、「ダイナマイト」を作ったきっかけが、「ツアーの1曲目になる曲がない」ってことだったんですよ。その時はアルバムが出てからのツアーというわけではなかったので、じゃあどういうツアーにするかということで、自分たちがやりたかった80'sのムードで作ったんですよね。そこから次の「WOLF VIBES」の時にアー写を撮り直して、よりファッションに寄ったというか。その写真と自分たちのテンションに合った音楽ということで作り始めて、みんなもそうだと思うんですけど、僕もその等身大な感じがしっくり来て、それが『RUNWAY』というところにつながったんですけど、だからけっこう自然な流れで今に至っているかなという感じですね。
──アー写から曲へ、ということもあるんですね。
YU 客観的に自分たちを眺めるきっかけというか、手法の一つというか。アー写もジャケットも写真も、僕らの中では一つの表現方法ですからね。バンドって、そういうパッケージで楽しめるものだと思うので、そういう意味での楽しみ方もしたいねと。
SHUKI 今までの僕らがやってきたことがけっこう幅広かったので、今年は逆にちょっと絞って僕ららしさを出していこうということで、「WOLF VIBES」の時から、「アー写の僕らに合った曲ってどういう曲だろう?」ということをイメージしながらやってきました。
──では、アー写の撮り方一つにもけっこう時間をかけているわけですね。
YU それも、「アー写をどう撮るか」というよりも「どこに行けば自分たちっぽいか」ということなんですよ。好奇心もあったりして、いろいろ試したくなる自分たちもいるんですけど、そこで自分たちの気持ちが先に行っちゃってクリエイターがついてこれなかったら意味がないんで、1回抑えるというか、向かう先を、自分たちらしさを追求するクリエイティブに集約しようと。詞も、音楽も、写真も全部そこに向かうようにしようと。そういう風にできたら、来年はより自分たちらしさを出せるよねというのを、年末ぐらいに考えてました。

CHOJI 今までは単発のクリエイティブ・ファーストだったんですけど、今回は僕らファーストで、それをクリエイティブに落とし込むという逆のやり方に集約していきましたね。
──では、今回はトータルで思い描いた形にできたわけですか。
YU そういう意味では、そうですね。もしかしたらそれ以上のものかも。今までは考えすぎてたんですよ。「これを出したらどういう風に見られるか」とか。そういうのの限界も感じてて。だから今回は具体的に「こうなるだろう」という予想はせず、いい意味でそういう外的な条件は無視して(笑)。たぶん、自分たちが心地いいと思うものが、自分たちのやりたいことなので、その心のセンサーみたいなものに注意深く目を向けて歌詞を書いたり、メロディーのアイデアを出したりしていきました。
世界での経験を通してバンドを成長させてくれた「PAINT」
──先ほどからちょくちょく出ている「PAINT」ですが、『ONE PIECE』の主題歌になったこともあって、アイドラがより広く知られるきっかけになったと思います。その影響をどう感じていますか?
YU 一番は、日本で今まで僕らのことを知らなかった人たちに届いたという驚きよりも、海外に行けたということの方が、自分たち的には大きいですね。あの曲によって、海外に行く機会が実際にできて、海外でのライブで「PAINT」以外の曲もメチャクチャ盛り上がったりしてくれてるのを見て、「ああ、これでよかったんだ」という自信につながったということの方が、あの曲から得たものとしては大きいかなと思いますね。

KENJI 海外でも活動していきたいという思いは当初からあったんですけど、この「PAINT」という曲を『ONE PIECE』を通して作ったことによって、いろんなところに行く機会にも恵まれましたし、日本でもフェスには出てますけど、それより大きな場所だったりで自分たちを試す機会が生まれて、その中でしっかりとしたパフォーマンスを発揮することが僕たちの糧になったと思うんですよね。これから日本で活動する上でも必要なプロセスだったし、勉強させてもらえたなというところで「PAINT」には感謝してます。
──海外のフェスで評価されたりすると、自分たちのやってきたことが間違いじゃなかったという気持ちにもなりますよね。
YU それはすごくなりました。どうしても自分たち4人のルーツは洋楽がメインで、「日本の音楽シーンに受け入れられるためにはどうしたらいいんだろう?」というところを試行錯誤してきた部分があるんですね。それがいい意味で吹っ切れたというか、今後もクリエイティブの実験として楽しみながらやる分にはいいんですけど、そこで変に頭を悩ませながら曲を作るのは、本来あるべき姿じゃないなと思っていて。僕が音楽でやりたいのは、その曲を聴いてテンションが上がったりとか、もっと本能的なところなんですね。「このビートでこの旋律だったらみんなが聴きやすいんじゃないか」みたいなことよりも、もっと本能的なところにたどり着けるような曲を作っていきたいんです。そういう意味では、こんな機会をもらって曲を作って、海外にも出してもらえたことで、変に考え過ぎる必要はないんだと、僕らがエネルギーを注ぐ場所はそこじゃないんだということが分かって。その結果、もっと僕たちらしいところに魂を注ぎ込むということに集中できるなと思いました。
──そういう意味でも「PAINT」は大きかったんですね。あの曲は「ザ・J-POP!」という曲調で新鮮でしたが、「アニソン」という側面は意識されたんですか?
YU しました。それで言うとあの曲って、「I Don't Like Mondays.さんに作ってもらいたい」と、僕らを名指しでいただいたオファーではないんですよ。まだそこのレベルに達してないという自覚は僕らにもあるし、そういう驕りはないんですが。ただそのチャンスはいただいたので、そこで僕らがそのチャンスを掴み取るためには、『ONE PIECE』という僕らが子供の頃から好きなコンテンツの良さを心から理解して、そこに寄り添えて、そのオープニングがより魅力的になる音楽じゃないと、僕らがやる意味がないと、すごく思ったんです。だからかなり研究して、でも僕らが奏でるものなので、どうしても僕ららしさみたいなものも出てしまうじゃないですか。そこは思いきりやろうとみんなで決めてやって、採用してもらったので。もしかしたら「アイドラっぽくないよね」って思う人ももちろんいるかもしれないし、そこから僕らを知ってくれた人もいるし。だから結果よかったなと思いますね。
──「らしくない」というよりも、正直「J-POPもガッチリやりこなすな」と思ったんですが(笑)。
一同 (笑)
YU ただ海外に行って思ったのは、世界の人たちって、「J-POP」だとか「洋楽」だとか、それすら考えてなくて、もっと本能的。
KENJI ジャンルがどうだとか言ってないよね。
YU 気付いてすらいないと思う(笑)。
──アルバムの話に戻りますが、前半は深めのアレンジの曲が多くて、終盤に「WOLF VIBES」「ダイナマイト」とアップテンポの曲が続きますよね。この構成というのは?
SHUKI やっぱり流れによって曲の聞こえ方も全然変わってくるので、一つひとつがよりよく聞こえるようにというのと、このアルバム自体、「僕らっぽさ」をより分かりやすく伝えたいというのがあったので、前半で特に今の僕らっぽいと思える曲を集めたというのもありますね。
YU 一番はやっぱり、「よく聞こえるには」というところですね。並びをミスると、同じ曲でも全然よく聞こえないので。そこを一番意識した結果、こうなりました。
──アルバムって、始まりと同様かそれ以上に終わり方も大事だと思うんですが、このアルバムではアガって終わるイメージですよね。
YU それで言うと「Beautiful Chaos」という曲は、もともと「ライブの最後の曲に似合うような曲を」ということで作ってたんです。しばらくの間、デモのタイトルも「ライブ最後の曲」ってなってたぐらいなんですよ(笑)。最後がバーッと広がっていくような曲なので、アルバムでも最後の曲になるのかなと思ってたんですけど、いろいろ並べ替えていった結果、「Summer Ghost」の流れからそこに入るのが一番よく聞こえるとなったので、そうしました。

CHOJI 「ライブの最後の曲」ということですけど、やっぱりシンセじゃなくてギターの方がバンド感を出せる楽器だと思うので、たくさんギターを入れました。その意味で、ライブでもやり甲斐のある曲になるんじゃないかなと思ってます。やっぱり「TONIGHT」はライブでもお客さんがすごく盛り上がるんですけど、それを超えるというか、また違う形でそういうのを提示できた曲になって、よかったなと思ってます。
──先ほども「ライブの1曲目になる曲がほしい」という話がありましたが、ライブの中での必要性みたいなところから作られる曲も多いんですか?
KENJI 今回、特に意識しましたね。前作の『Black Humor』を出した時はコロナ禍の中だったじゃないですか。みんなの聴き方も変わってきちゃって、ワイワイしたところで聴くというよりは、一人でじっくりという感じになりましたよね。だから僕らもけっこう試行錯誤して、「家でひとり聴きできるもの」というものに挑戦したんですね。そこから「Black Thunderbird TOUR」をやって、翌年はフェスとか海外でやらせてもらう機会があって、徐々に声を出せるようになった中で、「やっぱりライブって本来こうだったよな」というのがすごくあったんですよね。その中で、ライブをさらに楽しくできるような曲がほしい」というのはみんな思ってたと思うので、今回は特にライブでやるのが楽しみな曲が多いという印象ですね。
今回のアルバムで各メンバーが新たに挑戦したこととは?

──3曲目から6曲目は新曲が並んでいますが、「Beautiful Chaos」の次の「Strawberry Night」はESME MORIさんとの共作で、すごくダンサブルな仕上がりですね。
SHUKI これは、本当の原型はもうちょっと洋楽っぽかったよね。
KENJI そうだね。
SHUKI メロとかテンポ感は全然変わらないんですけど、今回のアルバムに向けてデモを何曲か作って、どれを入れようかという話をしていた中で、せっかくだから今年のトレンドっぽい、そのときしか作れない音楽も作りたいし、だったらどうせなら誰かと一緒にやりたいという話になって。僕とESME君は同い年なんですけど、今のトレンドに強い人とやりたいということでお願いしたら、快く受けてくださったんです。そこから僕らはデモを投げて、ただ「こうしてください」じゃなくて、極力ESME君の色を出したかったので、ホントに好きなようにやってくださいという感じで、そこから何回かやりとりして作り上げていった感じですね。
──共作ということでいうと、次の「conversation」もDPR CREAMさんの名前が入ってますね。
YU DPRという、韓国発で世界で活躍してるアーティストがいるんですけど、もともと僕らもすごくファンで、ライブとかも行かせてもらったりして動向をチェックしてるぐらいで(笑)、すごいクリエイティビティーなんですよね。アジアでこんなに世界に通用する人たちがいるんだなあということで、いつか一緒にやりたいと思ってる中で、たまたま、ひょんなことから「一緒にやれるよ」というお話をいただいて、是非ご一緒したいとお返事して、まずは編曲という形でとなりました。DPRの曲は全部聴いているので、DPR CREAMのよさが生きるような曲をデモの中から選んで作っていって、それに対して彼が「こういうのはどう?」という感じで返してくれて。今までだったら初めに決めたメロディーのまま最後まで行くんですけど、リアレンジされたものを聴いて「もっとこうした方がいいかも」ということで、けっこうメロディーも変えたりして、また彼もインスピレーションでいろいろ変えたりして。結局、この曲も自分たちだけだったら絶対生まれないよなというものになりましたね。DPRらしさもすごく出ていて、自分たちとしても「面白い曲ができたな」と思いました。
──今後も続いていきそうですね。
KENJI できれば嬉しいです。
YU できたら、ゼロから作るのもやってみたいなと思いますね。
──もう1曲の新曲が「Sin City」。こちらはビート感の強い曲ですね。
SHUKI そうですね。これはYUのファルセットが生きる曲がほしいなってとこからスタートして、声以外の要素が極力入らないように意識して作っていったんですけど、サビがパーッと開ける感じなので、その対比としてAメロ、Bメロはあんまり明るすぎないように……ダークまではいかないですけど、サビとのギャップを作ろうという感じにしました。ジャンル的に言うと「ディスコ」で、ディスコって昔からのイメージだとブラスが入ってたりして、照明も暖色系だったり、ブルーノ・マーズもライブではそういう感じでやってるんですけど、僕個人的には、僕らの今年のイメージが深い青だったりするんですね。だから明るすぎない印象の照明が映えるような曲を、イメージカラーというか、軸にして作っていったらけっこうトラックが作りやすくて。普通のディスコでいったらけっこう明るくなりがちなところを、「オレンジなのかもしれないけど、なるべく青に近づける」というか、そういうところを意識しました。
──この新曲を含むアルバムの中で、特に新しくやってみたことというのは?
YU 僕はDPR CREAMと一緒にやった「conversation」で、ラップのリリックをここまで本格的に書いたというのは初めてでした。今までは“ラップもどき”というか、あくまでバンドマンが書くリリックという感じだったと思うんですけど、せっかくDPRとやるんだったら、というのもあって。そこで気付いたのは、「普通の詞とは、使う脳が違う」ということでしたね。
──違いますか。
YU それぞれの難しさとか面白さがあるんですけど、本当に感情のままに言葉にできるのが、ラップ調のリリックのやり方なんだなというのを思いましたね。すごく楽しくやれて、だからこそ難しさもあったんですけど。あとは、普通だったらメロディーの音程が重視されるんですけど、ラップでは言葉だけの音程が、聴く人によりアプローチしてくるので、そのへんも、難しさであり楽しさでもあるのかなあと思いました。

KENJI 出来上がってみて思ったのは、今回はバンドらしさを大事にしようと言っていた中で、僕のベースは打ち込みの方が多くて(笑)。ドラムを生でやるか打ち込みでやるかの違いで、曲のバンドらしさってけっこう左右されると思うんですけど、今回は打ち込みっぽい曲でもSHUKIが生で叩いてる曲が意外に多いんですね。その中で、ちゃんとスピード感を出せるようにということで僕は打ち込みでやった曲が多いんですけど、そもそもベーシストなので、打ち込みよりは弾く方が得意なんですよ。だからすごく試行錯誤しました。『Black Humor』の時は邦楽というものをけっこう勉強したんですけど、今回は海外の打ち込みの曲をけっこう聴いたりして、「ベースの中でもこういう音色やフレーズがあるんだ」とか「こういう風に音をレイヤーすると、こう聞こえるのか」というのをインプットしたのを踏まえてアウトプットできたなと。そういうのが改めて勉強になりましたね。
──なるほど。
KENJI アルバムを通してだと「Sin City」が一番トライしてるというか。生のベースもスラップで入れてたりするんですけど、シンセベースの音が4つから6つ、セクションによってレイヤーされていて、それは本当にすごく実験的でしたし、僕の中でも「シンセベースってこういうものなんだ」というのを改めて考える、いい機会になったなという感じですね。

SHUKI 『Black Humor』の時は歌詞が伝わりやすいようにということで曲調から工夫して、そのために日本の音楽、その時にトレンドになってる音楽をいっぱい聴いたんですね。その中でやっぱり、AメロBメロサビというのが分かりやすい構成なんですけど、ボカロや宅録が流行ったりして、そういうルールにとらわれない方がいっぱい出てきて、そのへんの面白さをそこで学んで。洋楽って、自由な面もあるんですけど、形式的にはずっと一緒だったりして、変化が多すぎるものは少ないんですよね。転調とかも少ないし。という意味では今回のアルバム、特に新曲はあんまり頭で考えずに、その時いいと思うものをどんどん作ろうということで、洋楽だけ、邦楽だけという考え方ではできないような、けっこう自由な感じで作れたのはチャレンジというか、逆にそれがストレスなくて。聴いてる人も飽きずに聴けるものになったかなと思います。
──それはしかし、けっこうなチャレンジですよね。
SHUKI そうですね。考えるのを放棄したというか(笑)、カッコよければ何でもいいじゃん、っていう感じで作りました。
CHOJI 僕はどの曲にも、影響を受けたギタリストのフレーズとかを実は入れてたりしてて。「Summer Ghost」のエンディングはヴァン・ヘイレンだったり、「Sin City」もクール・アンド・ザ・ギャングのミュートリフを意識して弾いたりしてるんで、気付いてくれる人は気付いてくれるかなと。そういう風な楽しみ方もできるんじゃないかなと思います。「これはこれかな?」と思った人はツイッターなりで聞いてくれれば、正解を教えますんで(笑)。
「RUNWAY TOUR」ではより大きくなったバンド力を爆発させたい!
──アルバム自体の内容も充実してますが、同時に発売される「豪華盤」がDisc 2の楽曲もたくさんあるし、PHOTO BOOKも付属してて、文字通り豪華ですよね。
YU アルバムは2年ぶりになるんですけど、僕らはけっこう休まずに曲を作り続けてきたので、それが体感できたらいいなと。PHOTO BOOKとかも僕らのやりたい世界観が具現化できているので、そこも楽しんでもらえればと思います。
KENJI クリエイティブの統一という意味では、今までで一番できたんじゃないかと思いますね。
SHUKI この時代、音を聴くだけだったらCDである必要はないので、わざわざCDを出すということは、“もの”としても僕らの思いを伝えたいという意味で、僕らもけっこう気合いが入っちゃいましたね(笑)。
YU PHOTO BOOKに関しては、新しく一緒にやってるチームがあるんですけど、彼らとけっこう密に僕らの表現したい世界とかのことを話し合って、それをどう写真に落とし込むかというのは今まで以上に深くやりました。
──今までだって、ほかのアーティストやバンドと比べたらかなりこだわってる感じがありますが、それ以上なんですね。
YU そうですね(笑)。もっともっと突き詰められるところはあるなと思うんですけど、ようやく、僕らのやりたい世界観が実際のものとして世に出せる土台みたいなものができてきたなと思います。
──で、10月から12月にかけてはまたツアーですね。今お聞きしてきた中で、若干ヒントみたいなものもありましたが。
YU 僕らもまだリハーサルに入ってないので(※取材時点)、まだどんなものになるのかは分からないですけど、言えるのは、本当に去年とは比べものにならないぐらいパワーアップしているということですね。曲単体もそうだと思うんですけど、演奏もそうですし、バンド力みたいなものも海外での経験を通じて大きくなってるなと思うので、そういうものが爆発させられたらいいなと思ってます。
──繰り返しですが、海外での経験は本当に大きいですね。
YU 本当にそうですね。自分の中でも、枷みたいなものが取れた感じがします。
──ツアーと言えば、2月から3月にかけてはSELECTION TOURが行われましたよね。そこで気付いたことというと?

YU リクエストに本当に忠実にやろうと決めていたので、「バラードばっかりになったらどうしよう」とかいろんな懸念があったんですけど、やっぱり僕らのファンの方々は分かっていて、ちょうどいいバランスで曲をチョイスしてくれたので、ストレスなく楽しめました。さすが我々のファンだなと(笑)。
SHUKI 1位になったのが初期のアルバムに入ってる「LOVE YOURSELF」という曲だったんですけど……
YU あ、アレは意外だった! 癒やしを求めてるんだなと思いましたね。
KENJI あ、そういうことね(笑)。再生回数が多い曲が上に来るのかなと思ってたら、けっこう意外な結果になりましたね。
──今年の後半はツアーが中心という感じですか?
YU そうですね。ただ海外もあるし、まだ発表してないものもありますし。制作は一段落したので、基本的にはライブがメインにシフトしてくるかなと思います。まあ、曲もちょこちょこ作るとは思いますけど。
──その中で、今後こうしていきたいというのは?
YU やっぱりクオリティーを上げたいですよね。僕はボーカルのレベルをあと3段階ぐらい上げたいなと。
──3段階ですか。
YU 海外で活動していくとなると、バンドに甘えていられないというか(笑)。今までだったらノリで何とかできてたところも、よりクオリティーを求められるので。それは日本でもそうですけど。そこをレベルアップしていきたいなと思ってます。
KENJI 毎回、ツアーのたびに気づきがあって、成長もしていくと思うんですけど、今回久しぶりにライブを想定して作れたアルバムなので、いろんな経験も経て、とにかくこのツアーでバンド力をどれだけ引き上げられるかというのを徹底していきたいですね。海外も行くし、もっともっとバンドとしても成長していきたいと思ってます。
SHUKI 声が出せるツアーが久しぶりなので、本当に一体感が出せるような僕らのライブを作りたいし、それをもって来年の活動もなるべく迷いがなく進めるように、やりきりたいですね。
──毎年、「来年はこうしよう」という意識があるものなんですか?
SHUKI わりとありますね。
YU 今はアルバムができたばっかりですけど、もう僕の頭の中では「次はこうしよう」というのは何となくあります。
──それは素晴らしい。
YU ありがとうございます(笑)。僕は納期に遅れないタイプなので。
KENJI 早め早めは大事ですね。
──最後になりましたが、CHOJIさんはどうでしょう?
CHOJI せっかく『RUNWAY』というアルバムとそのツアーなので、ファッションを意識したライブを全国の皆さんにお届けしたいなと思っております。演出とかステージングとかも、もっと意味があるものになってくるかと思うので、楽しみにしていただければと思います。
──いろいろ楽しみなことが多いですね。ありがとうございました!
撮影 長谷英史

5th Album『RUNWAY』
2023.09.06 ON SALE
https://idlms.com/news/349401


I Don't Like Mondays. 2023 A/W TOUR "RUNWAY"
https://idlms.com/news/347726
【I Don't Like Mondays. WEB SITE】
https://idlms.com
【I Don't Like Mondays. YouTube】
https://www.youtube.com/idontlikemondaysofficial
【I Don't Like Mondays. Instagram】
https://www.instagram.com/idlms.official
【I Don't Like Mondays. Twitter】
https://twitter.com/IDLMs_OFFICIAL
【I Don't Like Mondays. TiKTok】
https://www.tiktok.com/@idlms_official?lang=ja-JP
【I Don't Like Mondays. Facebook】
https://www.facebook.com/rockidlms

- WRITTEN BY高崎計三
- 1970年2月20日、福岡県生まれ。ベースボール・マガジン社、まんだらけを経て2002年より有限会社ソリタリオ代表。編集&ライター。仕事も音楽の趣味も雑食。著書に『蹴りたがる女子』『プロレス そのとき、時代が動いた』(ともに実業之日本社)。